日本の「戦略思想不在の歴史⑽」『高杉晋作の機略縦横と突破力③』明治維新に火をつけたのは吉田松陰、徳川幕府を倒したのは高杉晋作である』★『男子は困ったということだけは、決していうものじゃない』
2017/12/01
明治維新に火をつけたのは吉田松陰であり、230年惰眠をむさ
ぼった徳川幕府を倒したのは高杉晋作である。
田中光顕の『維新風雲回顧録』を読み直して、改めて高杉の凄さを再確認した。不惜身命の精神である。
高杉に弟子入りして、謦咳に接した田中の回想録だけに迫力満点、「風雲児」高杉の神出鬼没、快刀乱麻、勇猛果敢な飄々としたその突破力を明らかにしている。
特に「男子というものは、困ったということは、決していうものじゃない」が高杉の不動の信念であり、岩をも貫ぬく革命精神であることがわかる。
田中光顕著『維新風雲回顧録』の高杉回顧録は無類におもしろい。Wiki田中 光顕https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%B8%AD%E5%85%89%E9%A1%95
坂本龍馬の盟友の中岡慎太郎は、「時勢論」の中で予言している。
「自今以後、天下を興さんものは、必ず薩長両藩なるべし、吾思うに、ちに、二藩の命に従うこと、鏡にかけて見るがごとし、しかして他日、天下近日の国体を立てて外夷(外国)の軽侮を絶つも、またこの二藩にもとづくなるべし、これまた封建の天下に功あるところなり」
事実、天下の風雲は、中岡の予言したように動いた。
この時、長州で田中光顕が最も世話になったのは、高杉晋作である。中岡は、「兵に臨んでまどわず、勝機をみて動き、奇をもって人に勝つものは、高杉東行、これまた洛西の一奇才」と称賛しているが、高杉は長州における人物のみならず、天下の人物であった。
最初、田中が高杉に会ったのは、1863年(文久3)、春、国もとから京都に出た時であった。
高杉は、当時、髪を剃って、クリクリ坊主になって、法衣のようなものをまとい、短剣を一本さしているだけの風体だが、それにはわけがある。
長藩(長州藩)では、彼を国元へかえして、政務座(藩政の中枢)に抜擢しょうとした。
ところが、高杉は役人になることは御免だと、いい張った。
藩の家老・周布政之助が、しきりに、すすめたが、なんとしても聞き入れない。
「拙者は、是非とも勤王の師を起こして、幕府を倒さずにはおかぬ、役人になることなどは思いもよらぬ」
周布は「といって、今、急に、そうはゆくまい、だんだん時勢がすすめば、足下(高杉)の望みどおりの時機が参ろう、まず・これから十年も待つことだな」
といった。
「しからば拙者に十年のおいとまを願いたい。さすれば、ほかにあって毛利家のために働きます」
「それほど、足下が熱心なら、たってとも参るまい、十年のおいとまはなんとかして、取り計らって進ぜる」
周布が、中に入ったので、君侯からもお許しが出た、そこで、彼は、すぐに、落籍を脱して坊主となったのである。
そして、高杉は「西へ行く人を慕うて東行く 我心をば神や知るらん」とざれ歌を詠んだ。
西へ行く人というのは、西行法師をさす。西行が隠遁したのを慕って、反対の東へゆくという心持ちは、神よりほかに知るものはないという意味。
田中と初対面の時は、正にこういう際であって、何でも場所は東山にある料亭で、高杉は、首に頭陀袋をかけていた。
芸者が、よってたかって、物珍しそうに、この坊主頭をからかいはじめた。すると、高杉は、坊主頭をたたいて、謡い出した。
「坊主頭をたたいてみれば 安い西瓜の音がする」
満座、笑いくずれてしまった。その飄逸な態度は、今もなお、田中の眼底にありありとのこっている。
田中は、はじめ中岡の使いとなって、長州から太宰府に転座した五卿を訪ねた。これが、八月一日で、翌々三日に到着してみると、五卿はほとんど監禁同様な御身の上、京都の模様やら長州の事情をちく一、申し上げようとした。
すると、五卿御守衛をうけたまわっている薩摩の肥後直右衛門が、面会を許そうとしない。
もっとも、その折、幕府では五卿を関東に檻送しようというので、大目付小林甚六郎なるものが、太宰府に来ていた。
肥後は、俗論派で、内々この一幕吏をはばかっていたらしい。どうしても、五卿に会わせぬというので、相手にならずと、田中も断念した。
「薩藩として、まことにけしからぬことだ、どういう所存か、京都に引き返し、とくと西郷にたださねばならない」
田中は土方桶左衛門(後の久元)に、意中をうちあけて、八日に長州へもどってきた。
そして、久しぶりで、石川清之助(中岡慎太郎の変名)とともに高杉に会見した。
この時の高杉は、坊主頭ではなく、意気軒昂、当たるべからざる勢い。奇兵隊の面倒もみていたし、海軍のことも世話をしていたし、ほとんど陸海軍総督といった地位にあった。
奇兵隊は、高杉の取り立てたもので、長州諸隊の根源となった。この騎兵隊の面々はさながら一州のがえん者 (ならずもの。無頼漢)の集まりだ、戦争がないと、一日も、じっとしていられぬ、命知らずの壮士の隊だ。通常のものでは、しょせん統御がむずかしく、高杉でないと、おさまらなかったものだ。
これについて、高杉はこういった。
「孫子に、大将、厳を先とすとある、自分が裏隊を取り立てた際には、まず法律を厳にし、これを犯すものには、割腹を命じた。はなはだ残酷のようであるが、一罪を正して千百人を励ます、しからずしては、壮士を駕御することは困難である」
したがって、奇兵隊の軍律は、簡単明瞭なもので、高杉の性格そのままだ。
『盗みを為す者は殺し、法を犯す者は罪す。この2ヵ条にすぎない。』
ある時、高杉が「ちかごろ感服つかまつる、どうか、この刀を拙者にお譲りを願いたい。たっての望みだ」と田中に頭をさげた。
「何としても、ご執心でありますか」
「いや、もう欲しくてたまらぬのであります」
「では、私にもお願いがあります、お聞きとどけ下さらば、さし上げぬものでもありませぬ」
「何んであるかいっていただきたい」
ここぞと、私がつめよせる。
「しからば、あなたのお弟子にしていただきとうござります」
「弱ったな、拙者は、人の師たる器ではない」
「それならいたし方ござりませぬ、刀は、お譲りはできませぬ」
「つらいな、ようし、そういうことなら、およばずながらお世話をすることにしましょう」
ようやく承知してくれたので、田中は、この一刀を高杉に贈り、彼の門下に入ったのである。
関連記事
-

-
日本リーダーパワー史(609)『110年前の伊藤博文の観光立国論』(美しい日本風景・文化遺産こそ宝)の 驚くべき先駆的な経済文化ビジネスセンスに学べー外国人を拒否せずおもてなしをすれば富国になれる
日本リーダーパワー史(609) 『安倍 …
-
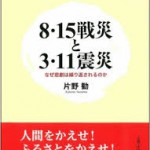
-
片野勧の衝撃レポート(74)★原発と国家―【封印された核の真実】⓾ (1974~78)ー原発ナショナリズムの台頭■カーター米大統領の核拡散防止政策
片野勧の衝撃レポート(74) ★原発と国家―【封印された核の真実】⓾ (1974 …
-

-
日本リーダーパワー史(803)ー『明治裏面史』★ 『「日清、日露戦争に勝利』した明治人のリーダーパワー、 リスク管理 、インテリジェンス⑲『日露戦争開戦6ヵ月前』★『6ヵ条の日露協定書を提出、露都か、東京か、の交渉開催地でもめる』
日本リーダーパワー史(803)ー『明治裏面史』★ 『「日清、日露戦争に勝利 …
-

-
日本リーダーパワー史(763)今回の金正男暗殺事件を見ると、130年前の「朝鮮独立党の金玉均ら」をバックアップして裏切られた結果、「脱亜論」へと一転した福沢諭吉の転換理由がよくわかる➀『金正男氏“暗殺”に「北偵察総局」関与浮上 次のターゲットに息子の名前も…』●『狂乱の正恩氏、「米中密約」でささやかれる米軍斬首作戦 正男氏毒殺の女工作員 すでに死亡情報も』
日本リーダーパワー史(763) 今回の金正男暗殺事件を見ると、130年前の「朝鮮 …
-

-
現代史の復習問題『日本の運命を決めた決定的会談』<明治維新から150年 >「ドイツ鉄血宰相・ビスマルクの忠告によって大久保利通は「富国強兵政策」を決めた』★『ビスマルクの忠告とは―西欧列強は万国法(国際法)と武力を使い分けるダブルスタンダード(二重基準)』
記事復刻<2018年は明治維新から150年 > &nbs …
-

-
『F国際ビジネスマンのワールド・ウオッチ⑱』『米NYタイムズ、162年目の大改革』 ◎『スマホは人間をばかにする?』
『F国際ビジネスマンのワールド・ウオッチ⑱』 &nb …
-

-
オリエント学の泰斗・静岡県立大学国際関係学部・立田洋司名誉教授の最終講義(1/31)を聴いたー『自然と人間文化の接点ーとくにキリスト世界とPasteralについて』
静岡県立大学国際関係学部名誉教授・立田洋司先生の教育生活40周年を …
-

-
『 地球の未来/世界の明日はどうなる』-『2018年、米朝戦争はあるのか』⑤『“認知症疑惑”が晴れてもなお残る、トランプ大統領の精神状態に対する懸念』★『トランプに「職務遂行能力なし」、歴代米大統領で初の発動へ?』★『レーガン元大統領、在任時に認知症の兆候 息子が主張』★『ブッシュ政権酔態、飲酒再開?プレッシャーに負けた 20代から深酒、乱闘で逮捕歴も 』
『2018年、米朝戦争はあるのか』⑤ 大統領1年で「うそ」2140回、1日平均6 …
-

-
「Z世代のための日本宰相論」★「桂太郎首相の日露戦争、外交論の研究①」★『孫文の秘書通訳・戴李陶の『日本論』(1928年)を読む』★『桂太郎と孫文は秘密会談で、日清外交、日英同盟、日露協商ついて本音で協議した①』
2011/08/29 日本リーダーパワー史(187)記事再編集 以下に紹介するの …
- PREV
- 日本の「戦略思想不在の歴史⑼」『高杉晋作のインテリジェンスと突破力②』●『上海租界地には「犬と中国人は入るべからず」の看板。ここは植民地である』★『内乱を抑えるために、外国の経済的、軍事的援助を受けることは国を滅ぼす』★『大砲を搭載した蒸気軍艦を藩に無断で7万両で購入幕府軍を倒すことに成功した、倒幕の第一歩!』
- NEXT
- 日本の「戦略思想不在の歴史⑾」『高杉晋作の大胆力、突破力③』★『「およそ英雄というものは、変なき時は、非人乞食となってかくれ、変ある時に及んで、竜のごとくに振舞わねばならない」』★『自分どもは、とかく平生、つまらぬことに、何の気もなく困ったという癖がある、あれはよろしくない、いかなる難局に処しても、必ず、窮すれば通ずで、どうにかなるもんだ。困るなどということはあるものでない』
