『池田知隆の原発事故ウオッチ⑲』「共同体自治」を基軸に再生を「内を開発する」ということ――
『池田知隆の原発事故ウオッチ⑲』
『最悪のシナリオから考えるー「共同体自治」を基軸に再生を
池田知隆(ジャーナリスト)
(福島原発問題で雑誌に書きました。私のホームページからPDF版も読めます)
「暴走する原発④「共同体自治」を基軸に日本再生を
――「内を開発する」ということ――
(月刊日本2011年9月号)
日本各地に放射能汚染が広がっている現状が次々と明らかになっている。しかし、司令塔であるべき政治は権力闘争に明け暮れ、迷走が続く。だが、国民の生命と暮らしを守っていくために、政治に絶望しているだけではすまされない。
「フクシマ」との長い苦難の時代に向けて、いま私たちに求められているのは、自らが地域の暮らしの在り方を考え、しなやかな「自立」の精神と共生のための「自治意識」を鍛えていくことではないか。
「フクシマ」との長い苦難の時代に向けて、いま私たちに求められているのは、自らが地域の暮らしの在り方を考え、しなやかな「自立」の精神と共生のための「自治意識」を鍛えていくことではないか。
○ 国の土台を固めること
「国は戦争に負けても滅びません。実に戦争に勝って滅びた国は歴史上けっして少なくないのであります。国の興亡は戦争の勝敗によりません、その民の平素の修養によります」
これは、内村鑑三の「デンマルクの国の話」の一節である(岩波文庫『後世への最大遺物・デンマルクの国の話』に収録)。北欧の国、デンマークが1864年、ドイツ・オーストリアとの戦争に敗れ、南部の肥沃な土地を失ったあと、再生していく話だ。
このときの国民的指導者ダルガスは「荒野を薔薇の花咲くところへ」と失意に沈む国民を鼓舞した。デンマークは農業と畜産と植林によって豊かな平和的な国へとよみがえった。ダルガスは工兵であり、土木学者であり、負け戦のさなかにも戦後社会への豊かな構想力をもつ詩人だった。
この話の副題に「信仰と樹木とを以て国を救ひし話」とつけ、内村が「戦いに敗れて精神に敗れない民が真に偉大な民である」と語ったのは1911(明治44)年1月、ちょう度100年前のことだ。日露戦争の勝利に沸き立っていたとき、内村の脳裏には国の興亡と国民精神を厳しく見つめる歴史観があった。
いま、「フクシマ」で核燃料(敵)は、封じ込めようとする人間の手を離れ、暴走を続けている。放射能汚染の拡散によって国土は失われ、国産食料の汚染度は増し、核との戦いは敗色濃厚の「戦中」状態だ。
半永久的に続く「見えない恐怖」に耐えて、私たちは生きていかなくてはならない。その精神的な支えとして、本誌前号で紹介した1946(昭和21)年年頭の「新日本建設に関する詔書」(昭和天皇と周囲の人々の熱く深い思いがにじんでおり、原文をぜひとも読んでいただきたい)に加え、「デンマルクの国の話」を心に刻んでおきたい。この話の最後に内村があげた三つの教訓の一つが冒頭の文章だ。
ダルガスがデンマークで植林活動を展開したように、先の戦争で焼け野原になった日本でも緑の山河をつくろうと全国各地でスギ、ヒノキを中心にした植林活動が繰り広げられた。「フクシマ」後、放射能汚染された東日本各地ではヒマワリ、ナタネの種をまき、少しでも土壌の汚染を除去しようというプロジェクトが広がっている。
復興にあたって内村は強い「信仰」心を強調したが、日本人には自然を深く崇拝する「愛郷心」がある。そして独特の無常観を通して度重なる苦難を辛抱強く乗り越えてきた。郷里を離れ、地震のない国に移住できる人もいるが、住民の多くは暮らしを営んできた地から離れることはできない。そして人が離れたとたんに山河は荒れる。人間が生きていてこそ山河は「ふるさと」となるのだ。
「がんばろう、日本」の掛け声があちこちで聞かれる。だが、なににがんばろうというのか。その焦点ははっきりせず、いつまでも宙に浮いているようだ。私たちは一人では生きていけない。亡くなった人たちを思い(共死)、地域の中で他の人たちと共に生きて(共生)いかなくてはならない。まずは足元の地域の暮らしを支えている「共同体」の見直しから出発すべきではないか。
○生存を求める「ネットワーク」
日章旗と「原発いらない」のプラカードが共に翻り、民族派ナショナリストたちが呼びかけた脱原発デモが7月31日、東京都内で行われた。放射能で郷土が汚染され、国民の健康は蝕まれ、山河を守るという民族派の原点に立ち戻っての行動だという。「3・11」以降、世論の針は「脱原発」の方向に大きく振れた。
集会やデモに人気俳優やアイドルがテレビ界のタブーを冒してまで参加し、放射能汚染から子供たちを守りたい一心の母親たちも多彩なネットワークを展開している。いまや右翼とか左翼の枠を超えて、「生存」を求める運動が生まれている。
これまで原発を国策として推進してきた「政・官・財・学」の一体的な日本の政治システムは必ずしも国民の暮らしを守ってくれるものではない。事故以来、そんな不信感が国民の間に急速に広がった。
気象庁は連日行っていた放射性物質の拡散予測を4月まで公表せず、多くの人はドイツなど海外で発表された予測を見ていたし、文科省管轄のSPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測システム)のデータも、緊急避難が求められた一般市民にすぐには知らされなかった。
それは「(情報を流せば)パニックになる」のを恐れてことだとみられるが、そのために汚染の酷い方向へ多数の住民が避難し、高濃度の放射性物質を不必要に浴びるという悲劇的なケースもあった。緊急避難時の情報公開の遅れは許されるべきことではない。
人間は五感を頼りに生きている。だが、放射能はこの五感ではわからない。「見たくないものは存在しない」とばかりに政府や政府に協力してきた学者たちは、事故の重大さや被曝の程度を極力軽くみせてきた。マスメディアは、最悪のシナリオには目をふさぐ解説や空虚な安心情報を流し、国民は日本がいまも「大本営発表」の社会であることを知った。いわゆる「原子力ムラ」といわれる原発推進集団では原子力三原則でいう「民主」も「自主」も「公開」も忘れられ、そこには「独善」や「従属」や「秘密」が横行していた。
そんな中で「原子力ムラ」とは一線を画した市井の科学者たちの研究活動やネットワークが市民の信頼を集めた。特にNHKのETV特集『ネットワークで作る放射能汚染地図』で、放射線医学の研究者の木村真三さんが、長年放射線観測の第一線に立ち続けてきた岡野眞治さんの全面的な協力のもと、震災の3日後から放射能の測定を始め、汚染地図を作成していく過程が紹介され、大きな反響を呼んだ。
西から東、北から南、と危険を顧みずに3000キロの距離を走り続けたその調査を通して、住民に一番に知らされるべき驚愕の事実が次々と示されたのだ。科学の専門家は良心をもとに独自にチームとネットワークをつくってデータを公開し、市民もまた正しい知識と自己判断をしなければならない。そのことを痛切に思い知らされた。
「フクシマ」を通してあぶりだされた日本の政治経済システム。それは、政界・官界・財界・学会・メディア界が、それぞれ自らの利益追求のためには大勢の国民の生命や生活の犠牲すらいとわない姿であり、虚妄の正義の上にたつ「利権の共同体」を構成していた。戦前、戦中、戦後と一貫して続いてきたそのシステムはいま、国民生活を重視した目線から大胆に改革されなくてはならない。その改革は、国内の人口や産業の再配置、教育制度の見直しなどを含めてのことだ。
東京電力が原発を管轄外の福島や新潟・柏崎に設置し、地方から中央へと電力を吸い上げてきたことにみられる中央集権主義からの脱却こそ、新しい日本社会に向けた改革の道筋にすべきだと思える。国家運営の基本をなすエネルギー政策の今後の在り方をめぐる議論は、そのままシステムのラジカル(根源的)な変革につなげていかなくてはならない。
○「共同体」本位の復興を
東日本大震災と1923(大正12)年に起きた関東大震災とは、震災前後の政治や社会情勢が似ている、といわれる。短命内閣が続くなどの政治の混乱、恐慌、不景気という社会的、経済的情勢を列挙してみると、その指摘もうなずける。関東大震災後、昭和の超国家主義へと流れていった悪夢を思い起こせば、今後の日本社会の動向への不安感がたちこめてくる。
震災後や戦時経済では、どうしても「合理化」という発想にひきずられる。困窮した財政を改善しながら経済運営していくためにエネルギーと産業配置を合理化し、資源を効率的に集中させる。政府は強力な権力によって「超合理化」を進める。ナチスドイツでも、表向きは「反近代」主義を掲げて民族精神を鼓舞する一方、実際にはアメリカ型のテーラーシステム(時間制、出来高制などの工場管理、労務管理の方式)を社会の隅々に導入した。生産性をあげて他国との競争に勝とうと国家総動員体制が築かれていったのだ。
その歴史的な経験をいま、しっかりと学びとらなくてならない。一番に守るべきものは国民の日常生活であり、復興のキーワードの一つは地域の「自立」である。権限を有する地方分権化、さらには法令発布権を拡大させて地域自治の内実を豊かにしていくことだ。これからの復興計画が経済効率に専念するあまりに地域の産業や文化を破壊しないように、国の「統制と集中」をめぐる動きに厳しい目を注いでいかなくてはならない。
明治維新以降の近代化の過程の中で、日本の政治経済は東京など数少ない大都市圏の利害と都合とによって国土の画一化がすすめられ、統制されてきた。これからは、日本列島における人口や産業の配置を見直し、そのうえで各地域の農業、水産業、地方工業を軸に、自立した個性ある経済圏(生産と流通と消費の完結型)を創り出し、それらの緩やかな連合体による政治経済システムの構築を進めていくべきだろう。
中央集権型のシステムに比べると、それは市場効率原理からは一見、非効率に見えるかもしれない。だが、各地域がそれぞれの個性を発揮しうる多様性を保持し、連携を取っていく国民経済のほうが、長期的には持続力があるのではないだろうか。なによりも疲弊している多くの地域で、いきいきとした活力を生みだしていくことが肝要だ。
大震災を機に、ここぞとばかりに農業・漁業などの経営規模を集約して大型化し、民間資本を導入し、効率的に経済開発を進めようという動きが目立っている。だが、将来的に「自立」の道を探っていくには、その地域の風土や生活に根ざした「共同体」の歴史と伝統を生かさなければならない。それこそが地域再生の中核になる。
震災で生き残った村の多くは、しっかりとしたコミュニティーが残り、古くから伝わるさまざまな知恵や経験をもとに生きてきた地域だった。生産者と消費者との顔が見える関係をもとにした「フェアトレード」的な仕組みなども取り入れ、地域の「共同体」本位の復興を目指していくべきである。
日本の政治経済システムの改革について、社会学者の宮台真司氏は「復興は食とエネルギーが手掛かりに共同体自治に向かうべきだ」と訴えている。欧州における脱原発、脱化石、自然エネルギーをめぐる動きは、単なる電源種をどう確保するかという問題ではない。
食をめぐるスローフード運動が、暮らしの在り方を問いかける「食の共同体自治」に発展してきたように、エネルギー問題も「自分たちで自分たちの社会のスタイルを決める」という「共同体自治」の問題というのだ。そして私たちの生活意識を「システム依存」から「引き受ける=自立」への転換を図るべきだするその主張は共感できる。
○「内を開発する」視点を
瀬戸内に浮かぶ小さな島でいま、「自然エネルギー100%プロジェクト」が進んでいる。中国電力が山口県上関町に建設する上関原発計画(2基、出力各137・3万キロワット)に反対する祝島の島民約500人分の電力を自然エネルギーでまかなおうという試みだ。
この島は、原発予定地から約4キロに位置する離島で、島の人たちは半農半漁で、びわやミカンなどの果実類なども作っている。中国電力の電気に依存しながら脱原発運動を続ける自己矛盾から脱し、自然・再生可能エネルギーで島全体を自立させ、全国からの支援の輪を広げる狙いだ。
この祝島のプロジェクトは、エネルギー問題を語るうえで、私たちの足元の生活のあり方を問い直さなければならないことを突き付けている。「脱原発」の道を探るにも、欧米型の自然・再生可能エネルギー政策の導入を求めていくだけであれば、官僚主導の「政・官・財・学」一体的なシステムとなった電力統制の改善という流れに抗しきれないからだ。
自然・再生可能エネルギーの開発、電力の発送電の分離が現実の課題として俎上にのってきたが、そのことを地域産業の活性化、地域おこしにつなげていくために各地方自治体、住民は積極的にその論議にかかわっていくべきだろう。
いまの日本には、関東大震災時の後藤新平のような強力なリーダーは見当たらない。それはまた、市民が積極的に政策に介入していく時代だと考えることもできる。復興の原点は地域であり、被災地の現場にある。数々の苦難を乗り越えてきた知恵や技術やアイデアもある。それを活用して、地域再生のサイクルを回していくのがすべての基本だ。各地域でさまざまな工夫ができるように政策選択の自由度を高め、コミュニティーと連帯を基礎に地域づくりを行わなくてはならない。
地域社会ではすでに経済格差が拡大し、人々をつなぐ絆は次々と断たれている。グローバル化がすすみ、「自己責任」が叫ばれるようになり、自殺や、孤独死、高齢者の所在不明、乳幼児への虐待の問題が噴き出てきた。近所の一人暮らしの高齢者がどう生きているのか無頓着で、乳幼児の虐待も見過ごされがちだ。「無縁社会」化という実態は定着しつつある。
その共同体としての地域の崩壊の淵に立ったとき、私たちはその現実をしっかりと見据え、地域を構築する個人としての自治意識を深め、そのうえで政治家を通じて行政官僚を使っていくという自治のシステムを確立していくほか、それらを打開する手立てはない。最後に内村の「デンマルクの国の話」の中のもう一つの教訓を引用する。
「善くこれを開発すれば小島も能く大陸に勝さるの産を産するのであります。(略)。富は有利化されたるエネルギー(力)であります。しかしてエネルギーは太陽の光線にもあります。海の波濤にもあります。吹く風にもあります。噴火する火山にもあります。
もしこれを利用するを得ますればこれらはみなことごとく富源であります。かならずしも英国のごとく世界の陸面六分の一の持ち主となるの必要はありません。デンマークで足ります。然り、それよりも小なる国で足ります。外に拡がらんとするよりは内を開発すべきであります」
デンマークでは1985年に原子力発電を放棄し、自然・再生可能エネルギーの比率(現在約28%)を高めている。日本とは人口規模も風土も異なり、デンマークのすべてがいいわけではない。
だが、「フクシマ」後の世界をどう生きるのかについて考えるとき、内村の「内を開発する」という視点を見失ってはならない。それは日本の生活思想、文化を見つめ直すことであり、私たちの「自立」と「自治意識」を鍛えることでもある。
池田知隆オフィシャルサイト
関連記事
-

-
『リーダーシップの世界日本近現代史』(293)★『安倍・歴史外交への教訓(5)』「大東亜戦争中の沢本頼雄海軍次官の<敗戦の原因>」を読む―鳩山元首相の「従軍慰安婦」発言、国益、国民益無視、党利党略、 各省益のみ、市民、個人無視の思考、行動パターンは変わらず
2015/11/08   …
-

-
『リーダーシップの日本近現代興亡史』(213)記事再録/『 日本海軍トップリーダー・山本五十六の指導力と人格について、井上成美が語る』★『昭和18年9月25日発行の「水交社記事」(故山本元帥追悼号)より井上成美中将の「山本元帥の思い出』を再録』
2010/06/28 日本リーダーパワー史(58)記事再録 …
-
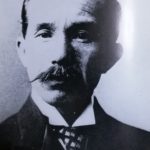
-
『オンライン講座/日本興亡史の研究 ⑰ 』★『日本最強の外交官・金子堅太郎のインテリジェンス』★『ルーズベルト米大統領をいかに説得したか] ★『大統領をホワイトハウスに尋ねると、「なぜ、もっと早く来なかったのか」と大歓迎された』★『アメリカの国民性はフェアな競争を求めて、弱者に声援を送るアンダードッグ気質(弱者への同情心)があり、それに訴えた』
2011-12-19 『ルーズベルト米大統 …
-
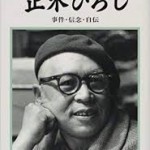
-
『日本一の刑事弁護士は誰か!」『棺を蓋うて』ー冤罪救済に晩年を捧げた正木ひろし弁護士を訪ねて』★『世界が尊敬した日本人―「司法殺人(権力悪)との戦いに生涯をかけた正木ひろし弁護士の超闘伝12回連載一挙公開」』
2017/08/10 『棺を蓋 …
-

-
日本リーダーパワー史(788)「国難日本史の復習問題」 「日清、日露戦争に勝利」した明治人のリーダーパワー、リスク管理 、インテリジェンス⑤』★『日本史の決定的瞬間』★『撤退期限を無視して満州からさらに北韓に侵攻した傍若無人のロシアに対し東大7博士が早期開戦論を主張(七博士建白書事件)』★『七博士建議書の全文掲載』●『現在日本を取り巻く地域紛争の激化―北朝鮮・中国の軍事エスカレーションと比較しながら、この提言を読む』
日本リーダーパワー史(788) 「国難日本史の復習問題」 「日清、日露戦争に勝 …
-

-
『Z世代のための日本戦争学入門④』★『平和時に戦争反対はやさしい。戦争時に平和を唱えて戦った軍人は・③』★『日米戦争の敗北を予言した反軍大佐/水野広徳』★『日米非戦論・軍縮を唱え軍部大臣開放論を唱えた』
2018/08/20 /日米戦争の敗北を予言した反軍大佐、ジャーナリスト・水野広 …
-

-
百歳学入門(109)医師・塩谷信男(105歳)の超健康力―「正心調息法」で誰でも100歳まで生きられる
百歳学入門(109) 医師・塩谷信男(105歳)の超健康力―「正心調息法」で誰で …
-

-
『F国際ビジネスマンのワールド・カメラ・ウオッチ(103)』「パリぶらぶら散歩」③―街中を歩くと、 微笑はモナリザだけではないな、と感じました。妙齢のご婦人が微笑で返して来るのです>
『F国際ビジネスマンのワールド・カメラ・ウオッチ(103)』 「パリぶらぶら散歩 …
-

-
日本メルダウン脱出法(639)『地方創生の空念仏』<借金地獄を作った「自民党政治」は徳川時代の「藩財政再建の神様」上杉鷹山、恩田木工、山田方谷にこそ学べ
日本メルダウン脱出法(639)『地方創生の空念仏』- <借金地獄を作った「自民党 …
-

-
歴史張本人の<日中歴史認識>講義」➉袁世凱顧問の坂西利八郎 が「(支那(中国)を救う道」を語る➉
日中両国民必読の歴史張本人が語る 「目からウロコの<日中歴史認識>講義」➉ &n …
