<衝撃深層レポート①>地名学が教える尖閣・竹島の真相はこうだ(上)楠原佑介(地名情報資料室主宰)
<衝撃深層レポート①>
『この地名が危ない!』で注目の地名学者が、尖閣・竹島が日本固有の領土
たるゆえんを懇切に解き明かす
地名学が教える尖閣・竹島の真相(上)
楠原 佑介(地名情報資料室主宰)
<季刊『日本主義』2012年秋号(第19号)掲載>
朝貢・冊封関係とは何か
具体的な地名の話に入る前に、明・清朝と琉球王国との関係について解説しておく。「琉球」という国名(地名)は漢字「陸」の漢音リクを一字一音で「琉」と「球」の文字に宛てたもの。
今年八月の香港船の魚釣島接岸以降の一連の反日デモに参加した中国人の中には、「沖縄も中国のものだ!」と叫ぶ連中も見られた。その主張の根拠は、①沖縄(琉球)は明・清両朝と冊封関係にあったから、中国の属国である。②漢字で「琉球」と書くこと自体が中国文化圏に属した証明で、すなわち中国が主権を主張する対象になる――というものである。
冊封関係にあったから中国の支配圏だという論は、近代というものをまったく理解していない考え方である。欧米列強の植民地主義を弁護するつもりはないが、少なくとも封建的帝国主義による少数民族支配を打破したという点では、歴史の進歩であった。
第一次世界大戦後のヴェルサイユ会議では、「民族自決」原則が唱えられ、少なくとも東欧においては民族国家群が独立した。この流れは、その後の世界史の主潮流となった。ひとり中国だけが封建王朝時代の冊封関係を維持できるわけがない。
漢字文化圏を即、中国の支配圏と見るのも、言語文化というものを知らない暴論である。二〇〇五年に中国全土で吹き荒れた反日暴動のさい、デモの様子を報道するTニュ―スの画面に、「独自の文字を持たないクセに!」と書かれたプラカードがあるのを見かけた。何という野蛮な発想だろう。
西ヨーロッパの諸国語はローマ字で表記される。もしイタリア人が西欧各国の国民に、「お前ら自前の文字もないクセに!」と叫んだら、イタリアは西欧社会から排除されるだろう。
ギリシャと東欧で使われるキリル文字の関係も、まったく同じである。
文明・文化というものは、必ず伝播する。その伝播先の国々を支配圏とするという考え方は、古代封建制・古代奴隷制の社会に戻れ、というのか。
中国人に言っておく。――あなたたちの祖先は、数々の文化・文物を発明・発見した優秀な民族だった。だが、その末裔たちはそのことに自己満足し、周辺の弱小民族を「東夷南蛮西戎北狄」と見下し、結果、その周辺蛮族に攻め入られて征服王朝を樹立され、二、三百年ごとに易姓革命があっても「眠れる獅子」と化していったのではないか。
以下に述べるように、中国人は今でも「漢字を使っている民は我々の属国であり、漢字地名の土地は中国領」と思い込んでいるらしいフシがあるが、それは大いなる錯覚である、と宣言しておく。
我々日本人は、平安時代まで中国から多くのものを教わった。だが、その後は異国の漢文化を咀嚼して自己のものとし、国風文化を築き上げた。漢字にしても、その音や音義だけでなく訓(意味)を十分に理解し、さらに仮名文字を発案して漢字仮名混じり文という独自の文章作法を編み出した。
仮名文字の発明は、西洋文化という新しい異文化の受容に画期的役割を果たした。原語をカタナ名で表記してその出自を確保し、その意味を翻訳して漢字二字の熟語を新考案した。
現在、漢字世界で使われる「社会」・「共和」・「共産」などという多くの観念語は、幕末から明治にかけて日本の知識人が原語のヨーロッパ語と漢字とを格闘しながら考案したもんである。
もっとも、この風はやがて日本人の社会にヨーロッパ語・漢字が進んだ言語であり、和語は前時代的な劣った言葉という誤った評価を定着させた。とくに地名の場合、和語起源の地名を嫌い漢字二文字の新地名に変えるという「非文化的」政策を導いてしまった。
「尖閣」は英語からの翻訳地名
韓国大統領の日本領竹島への上陸、香港在住の保釣連盟活動家らの尖閣上陸を受けて東アジアに剣呑な空気がみなぎった八月中旬、中国・山東省で日本語教師をしているという知人の知人と出会った。
私が地名問題をやっていると聞くと、彼は、「私の中国人の教え子の中には、〝尖閣〟は中国人がイギリス海軍に教えた地名だ、と主張する者がいますよ。本当ですか?」と尋ねてきた。
本誌二号(平成二十年四月)の拙論で指摘しておいたが、「尖閣」という地名は日本語(沖縄語)のオリジナルな地名ではない。
一八四五年六月、イギリス海軍のサマラン号(ベルチャ―艦長)が現・尖閣諸島付近で測量し、現在の北小島・南小島に上陸し天測した。この測量生家はイギリス海軍作成の海図に記載されたが、両島にそそり立つ岩峰群をキリスト教の教会の尖塔群に見立てて島名をPinnacle Islandsと命名した。
前記の本誌第二号の拙論では、このPinnacle Islandsの名を日本語(漢語)で「尖閣」と翻訳したのは沖縄師範学校教師の黒岩恒で、明治三十三年に発表した論文で現・尖閣諸島全体の総称として使い始めた、と述べた。
だが、もう少し厳密に述べると、「尖閣」の名はすでに明治六年に海軍水路部刊の「台湾水路誌」に現・南小島に「尖閣島」の名を記し
明治一九年刊の「水路誌」には現在と同じく島々の総称として「尖閣群島」の名を使っている。
だが、もう少し厳密に述べると、「尖閣」の名はすでに明治六年に海軍水路部刊の「台湾水路誌」に現・南小島に「尖閣島」の名を記し
明治一九年刊の「水路誌」には現在と同じく島々の総称として「尖閣群島」の名を使っている。
黒岩恒は、あるいは水路誌の使用例を承知していなかったのかもしれない。
明治初期、日本政府はまだ詳細な海図を作成する能力はなかった。現在でもそうだが、海図は元図作成国の了解のもと、それを写して作ることができる。海図記載の地図情報も、元図から翻訳するのが通例だから、この段階でPinnacle Islandsを「尖閣」と翻訳したのであろう。
なお、中国人学生のいう「中国人がイギリス海軍に〝尖閣〟の名を教えた」という主張は裏付けが取れない。もしそれが事実なら、現・尖閣諸島を「尖閣」と書いた地図か文献がなければならないが、古代からの膨大な文献資料を博捜する余力は私にはない。
状況から考えれば、漢語「尖閣」をPinnacle Islandsと英訳し、それをまた日本の海軍水路部がまた「尖閣」に戻すという作業があった可能性はかぎりなく少ない、と思う。
一九世紀、イギリス海軍は世界中の海に出没し、自分勝手に海図を作っていた。その際、現地人の教えてもらった地名を英訳して使うというケースは、ほとんどなかったのではないか。もし現地語の地名を採用するのであれば、英訳などしないで発音通りにアルファベット表記したはずであろう。
むしろ、北小島か南小島に上陸した測量隊員が、鋭く尖った岩峰を見上げて故国の教会のPinnacle になぞらえた、というほうが多いにありうる。
翻訳地名は無数にある
中国人たちはPinnacle にせよ「尖閣」にせよ本来の日本語ではないから、日本人のものではありえない、と主張したいらしい。だが、これは地名の成立ちに対する完全な誤解である。
日本では、外国語起源の地名がたくさんある。北海道北斗市など平成の大合併で誕生した新市町名はさておき、小笠原諸島に属する火山列島の硫黄島は欧米船(一説にクック探検隊とも)によって発見されて噴気孔から立ち上る硫黄臭から Sulfur Islandと命名された島名を明治二十四年に日本領とするに当たって「硫黄」と漢字訳されたものである。
また伊豆諸島南部のべヨネ―ズ列岩は嘉永三年、フランス艦べヨネ―ズ号によって発見されたことにより、その南の須美寿島はアメリカ人だったかイギリス人だったか、スミス船長の名による。フランスやアメリカやイギリスは、その島名が自国語起源だからといって俺たちの島だなどとは言わない(そんな主張をすれば、世界中から「何と野蛮な!」と軽蔑されること必至だ)。
沖縄漁民の呼んだ島名
ところで、現在の尖閣諸島には古くから沖縄漁民が命名した二つの島名があった。其の一つはユクン・クバ島、もう一つはイーグン・クバ島である。ユクンとは琉球語(沖縄方言)で「魚」のこと、イーグンとは八重山方言で「銛」のことである。したがって、銛のように鋭く尖った岩峰がいくつも並ぶ北小島・南小島がイーグンで、魚釣島のほうがイーグンだった。
なぜ「魚島」と呼ぶのか。森が茂る島の土地にはミネラル分が豊富で。島の沿岸にはプランクトンが湧く。それを餌にする大型漁の稚魚や小型魚が集まり、それを追ってマグロ・カツオなどの大型魚も集まる。
この理屈は大洋に浮かぶ流れ藻が一種の漁礁の役目を担って、大型魚の釣り場になるのと同じである。
したがって、本来のユクン(魚)島とは「魚が集まる島」のことである。それは瀬戸内海中部の燧灘に浮かぶ魚島が、内海では大型魚のタイの好漁場になるのと同じである。
瀬戸内海の魚島はタイの釣り場ではなく、周辺に集まるタイを縛り網漁で漁獲する。同じく、尖閣諸島の魚釣島も、マグロやカジキやカツオを陸から釣竿を垂らして釣る島ではない。
沖縄本島の方言が島名として記録されているのは、次のような事情による。本島南部の糸満市は、今でも漁業が主産業だが、漁民らはサバニという名の独特の刳り船を操って、南シナ海や北太平洋へ何百キロも出漁し、突ン棒漁や追い込み漁で漁獲した。当然、尖閣諸島周辺も彼らの漁場だった。
「釣魚台地」という名所
では、陸から竿を垂らして釣るわけではないのに、なぜ「魚釣島」という島名が定着したのか。それは、以下のような故事による。
『史記』斉太公世家が伝えるところでは、殷末周初の政治家・呂尚が世に受け入れられず渭水(黄河の支流。長安近くを流れる)のほとりで一人釣りをしていたところ、周の文王に見出されて軍師に迎えられ、のち周の傘下で斉の王侯に出世するという伝説的出世譚がある。「太公望」という言葉はたいがいの日本人は知っているが、中国では知らぬ者とてない有名な話である。
その渭水のほとりの釣りをしていた場所を釣魚台という。中国事情に詳しい友人によると、中国では北京の釣魚台は天安門西方の海淀区にあり、金朝の章帝が設置し清朝時代に周辺が玉淵潭として拡張整備されて水辺の憩いの場となっているという。
中国では大都市ならずとも中規模程度の都市でも、たいてい「釣魚台」という名の場所があり、実際に竿を垂れる人影が絶えないという。まあ、日本でいえば、「歌枕名所」といった存在なのだろう。
日中間・琉中間の「冊封」関係
だから、「釣魚台」本来のロケーションは島ではなく、内陸の河畔、百歩譲っても湖畔・池畔でなければならない。
そもそも、どの国の漁民であっても大洋の孤島で釣りなどはしない。磯釣りなどという遊漁法が成立ったのは、日本では高度経済成長期、レジャーとして始まったものである。
その点に、中国側、とくに中国の民衆がことの経緯を無視して執拗に「釣魚嶼は中国固有の領土」と主張するに至るポイントがある、と見る。
その経緯の分析に入る前に、前近代における東アジア的国際秩序だった朝貢―冊封関係について、私なりの解説をしておく。
冊封とは中国の皇帝が周辺蛮族の王を臣下として認め、その進貢を受ける代わりに下賜品と爵位・称号・暦を授けるというシステムである。中国の専制帝国側には周辺蛮族社会の安定化を通じて中華社会の権威を確立し、もって東アジア全体の安静を保持するという目的があった。中国から「東夷・南蛮・西戎・北狄」と蔑まれた周辺蛮族にとっては、自らの権威に対するお墨付きを獲得し権威を高めるという効用があった。
ちなみに、後漢の西暦五七年、倭の奴国が朝賀して「漢倭奴国」の金印を授与された件、魏・呉・蜀三国が抗争した三国時代、「親魏倭王」の印授を与えられた卑弥呼の邪馬台国、西暦四二一年、倭王・讃が宋に朝賀し「安東将軍・倭国王」の号を授けられた件などはその一例だったろう。
あるいは、推古朝の西暦六〇〇年から始まった遣隋使、舒明天皇二年に始まった遣唐使も、朝貢―冊封関係の一例とみてよい。ただし、遣唐使の派遣は平安時代前期の承和元年(八三四)の第一九回を最後に途絶え、以後、日本は東アジア世界の中で独自の政治体制を築き、文化的には国風文化の時代に入ってゆく。
冊封というシステムは、古い時代には中華帝国を中心とした国際政治・外交的側面が色濃かったようだが、中世になると文物の交流、つまり貿易関係の側面が強くなってくる。
応永八年(一四〇一)、室町幕府第三代将軍・足利義満が将軍職・太政官職を辞して一介の僧の身分で遣明使を派遣、建文帝から「日本国王」の冊封を受けた。
これにより室町幕府、のち社寺や細川氏・大内氏などの有力守護大名によって勘合貿易が行われるようになる。ただし、中世の日中関係はその経緯と実態からも明らかに、政治的権威の確などにはまったく無縁だった。文化交流という要素はあったが、端的には倭寇の猖獗に対し安定的な貿易を確保するためだった、と、見てよい。
琉球では 中山王・察度の代の一三七二年、明朝に初めて進貢船を派遣し冊封を乞うた。明の年号では建徳五年、日本では南北朝期になる。
一方、明の永楽帝によって琉球・中山王が初めて冊封を受けるのは、一四〇四年(明の永楽二年)のこと。足利義満の遣明使派遣の三年後であった。
(つづく)
楠原 佑介
一九四一年、岡山県生まれ。京都大学文学部卒業。出版社編集部退職後、地名研究家として活動。「地名情報資料室・地名110番」主宰。住居表示・市町村合併などによる地名の変更に警鐘を鳴らす。主な著書に、『「地名学」が解いた邪馬台国』(徳間書店)。『こんな市名はもういらない!』(東京堂出版)。『こうして新地名は誕生した!』(ベスト新書)。『この地名が危ない』(幻冬舎)。『古代地名語源辞典』(共著、東京堂出版)。『地名用語語源辞典』(共著、東京堂出版)。『地名関係文献解題事典』(共編、同朋舎出版)など多数。
関連記事
-

-
『日本戦争外交史の研究』/『世界史の中の日露戦争』㉒『開戦3ゕ月前の「米ニューヨーク・タイムズ」の報道』★『国家間の抗争を最終的に決着させる唯一の道は戦争。日本が自国の権利と見なすものをロシアが絶えず侵している以上,戦争は不可避でさほど遠くもない』★『ロシアが朝鮮の港から日本の役人を締め出し、ロシアの許可なくして朝鮮に入ることはできないということが日本を憤激させている』
『日本戦争外交史の研究』/ 『世界史の中の日露戦争』㉒ 『開戦3ゕ月前の「米 …
-

-
『リモートワーク/外国人観光客への京都古寺動画ガイド』(2016 /04/01)★『日本最大の禅寺』妙心寺は見どころ満載,北門から参拝』★『退蔵院の枯山水の禅庭園を観賞、ワンダフル!』
★5外国人観光客への京都古寺ガイドー『日本最大の禅寺』妙心寺は見どころ満載,北門 …
-
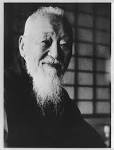
-
『オンライン講座/三井物産初代社長/益田 孝(90歳)晩年学』★『『千利休以来の大茶人・「鈍翁」となって、鋭く生きて早死により,鈍根で長生きせよ』★『人間は歩くのが何よりよい。金のかからぬいちばんの健康法』★『 一日に一里半(6キロ)ぐらいは必ず歩く』★『長生きするには、御馳走を敵と思わなければならぬ』★『物事にアクセクせず、常に平静を保ち、何事にもニブイぐらいに心がけよ、つまりは「鈍」で行け。』
2012/12/06 人気記事再録/百歳学入門(59) …
-

-
世界リーダーパワー史(40) 『世界の偉人の最期/中国共産革命を実現した毛沢東と周恩来のコンビの最後の葛藤』★『人民に愛され現役総理 のまま逝った不倒翁/周恩来』★『周恩来は「死んだら火葬にして、その灰を全国土に撒いてほしい」と遺言した』
2010/02/19 「 リーダーパワー史 …
-

-
Z世代への遺言「東京裁判の真実の研究①」★『東京裁判』で裁かれなかったA級戦犯は釈放後、再び日本の指導者に復活した』
『A級、BC級戦犯の区別は一体、何にもとづいたのか』★『日本の政治、軍部の知識ゼ …
-

-
『オンラインぶらり動画旅行/明治維新の源流/山口県萩市の『松下村塾』への旅①』★『日本の聖地ー萩藩主毛利氏の廟所(萩市の東光寺)500基の灯篭と眠る志士たち』★『明治維新発祥の地ー吉田松陰の『松下村塾」、山口県萩市の松陰神社境内』
2015/04/02 明治維新のふるさとー山口県萩市の …
-

-
★『 地球の未来/世界の明日はどうなる』 < チャイナ・メルトダウン(1057)>『劉暁波弾圧/獄死事件と、約120年前に日清戦争の原因となった「上海に連れ出して殺害した国事犯・金玉均暗殺事件」を比較する』★『中国・北朝鮮には<古代中華思想>による罪九等に及ぶ族誅(ぞくちゅう)刑罰観が未だに続いている』
★『 地球の未来/世界の明日はどうなる』 < チャイナ・メルトダウン(1057) …
-

-
『F国際ビジネスマンのワールド・ニュース・ウオッチ(148)』「ISと云うイスラム原理主義組織の現在の破壊力、 近未来の戦闘能力がどの程度のものになるのか?」
『F国際ビジネスマンのワールド・ニュース・ウオッチ(148)』 「 …
-

-
世界/日本リーダーパワー史(894 )ー『米朝会談前に米国大波乱、トランプの狂気、乱心で「お前はクビだ」を連発、国務省内の重要ポストは空っぽに、そしてベテラン外交官はだれもいなくなった。やばいよ!②」
世界/日本リーダーパワー史(894) トランプ政権の北朝鮮専門家、広報部長、ス …
-

-
梶原英之の政治一刀両断レポート(2)『原発事故が菅下ろし政局の主役だった!ー原発解散になるとみる理由』
梶原英之の政治一刀両断レポート(2) 『原発事故が菅下ろし政局の主 …
