日本メディア検閲史(下)
1
03年7月
静岡県立大学国際関係学部教授
前坂 俊之
1 CHQ占領下の検閲・事前検閲から事後検閲へ
1945(昭和20)年8月15日、日本はポッダム宣言を受諾して、無条件降伏した。長
い言論不自由の時代がやっと終わったかと思われたが、GHQ(連合軍総司令部)によ
って再び検閲は続行された。
9月12日、GHQ は「新聞記事その他、報道取締りに関する件」、同21日には10ヵ
条からなる「プレス・コード(新聞規約)」を発表した。
報道は真実を厳格に守ること、公安を害する事項は掲載しないこと、連合軍に対し
て虚偽、破壊的な批判をしないこと、記事は事実に即して記述し、編集上の意見は完
全に払拭することーなどの内容であった。
このプレス・コードが約六年半の占領期間中の日本の新聞、雑誌のいわば〝憲
法″であった。
9月29日、各紙朝刊の一面トップにモーニング姿の天皇と開襟シャツで軍服のマッカ
ーサーが並んだ写真が掲載された。日本が降伏し、真の支配者が誰であるか、一目
でわかるこの写真に対して、情報局は即日発行禁止処分とした。
この措置に怒ったGHQ は発禁を解除させ、同日付で「新聞言論の自由に関する追
加措置」を出して、戟前に公布され、言論の自由をがんじがらめにしていた12の法令
を直ちに撤廃させた。
占領軍の検閲は1945(昭和20)年10月から48年7月までは「事前検閲」がおこな
われ、それ以後は左翼的な総合雑誌を除いて 「事後検閲」 にとってかわった。49
年末以降は総合雉詰も「事後検閲」となった。
検閲については、戦前の日本の検閲のように、○○とか××の伏字や空白によって、
明らかに検閲や削除がおこなわれたことが読者にわかるやり方を禁じ、別の言葉に
言い換えさせたり、文章をまったく書き換えさせ、検閲したことがわからない巧妙な方
2
法をとった。
2 GHQ の検閲基準
GHQ は「プレス・コードに基づく検閲の要領にかんする細則」を通達したが、それで
は発行者は各出版物を2部ずつ民事検閲局(CCD)へ検閲のために持参する、検閲
事項を暗示することを禁止、大東亜戦争、大東亜共栄圏、八紘一宇、英霊のような戦
時用語を避けるーなどの内容であった。
<実際にどのような記事がこの検閲によって不許可、削除となったかというと、次の
ようなものであった>
米兵の暴行事件▽米兵の私行に関して面白くない印象を与える記事▽進駐軍将校
に対して日本人が怨恨、不満を起こす恐れのある記事▽食糧事情の窮迫を誇大に
表現した記事▽連合軍の政策を非難する記事▽国内における各種の動きにマッカー
サー司令部が介在しているように印象づける記事―などであった。
これに対して、新聞社は戦前のきびしい言論統制に慣れていたので、アメリカ兵を
白い大男だとか、黒い大男などと表現し、ジープを小型自動車などと言い換えて記事
に書き、検閲の網の目を巧みに逃れて報道した、という。
GHQ の検閲は一般国民にはわからない形で巧妙におこなわれ、1948(昭和23)
年ごろでも、GHQ の検閲人員370余名、日本人の嘱託5700余名という、膨大な人
員で、新聞、通信社の紙面化される予定の一切の記事がチェックされ、その数は新聞
記事だけで一日約5000本以上にのぼっていた(高桑幸吉『マッカーサーの新聞検
閲』読売新聞社、1984年、10頁)。
検閲の結果、パスせず、保留されたり、一部削除されたり、不許可でボツになった、
いわゆる「事故ゲラ」は正確な数字はないが、全体の5-10%にのぼった、という(高
桑、前掲書、29頁)。
戦前のきびしい言論統制から一転し、戦後の「アメリカは言論の自由を保障する」と
いう裏で、このような巧妙なやり方での検閲が実施されたのである。
以上、約80数年問にわたる検閲の歴史を眺めてきたが、政府、権力による言論統
制に対して、新聞、出版社などのメディア側の抵抗は残念ながら、ほんのわずかしか
3
なく、表現の自由、言論の自由への戦いは数少ない。
逆に、自主検閲、自己検閲によっていち早く克服していったのである。
3 現代の検閲は『自己規制』・安保からベトナム戦争報道
1960(昭和35)年、戦後最大の国民的闘争と言われた60年安保闘争が起こった。
6月15日、国会周辺を取り囲んだ学生、デモ隊が国会構内に乱入し、機動隊と激しく
衝突して、流血の惨事を引き起こし女子学生1人が死亡、300人以上が負傷した。こ
の2日後に在京の新聞社7社(朝日、毎日、読売、日経、サンケイ、東京、東タイ)は
朝刊一面に「暴力を排し議会主義を守れ」と題する共同宣言を掲げた。
「流血事件は、その事の依ってきたる所以を別として、議会主義を危機に陥れる痛
恨事であった。……いかなる政治的難局に立とうと、暴力を用いて事を運ばんとする
ことは断じて許されるべきではない」と全学連の行動をきびしく批判した。
この共同宣言はその後、地方紙48紙にも転載された。空前の勢いで盛り上がって
いた大衆運動で国民の間に、安保を強行採決した岸内閣の退陣要求が圧倒的に大
きくなり、新聞もこれを支持していただけに、突然手のひらを返したものであった。
「その事の依ってきたる所以を別として」「争点をしばらく投げ捨て」とデモ隊の暴力
だけを非難して新聞の姿勢は180度逆転してしまった。戦争中、死んでいた新聞は、
この共同宣言によって、再び死んだとも批判された。
「安保で死んだ新聞はベトナム戦争でよみがえった」と言われたが、1965(昭和4
0)年にはベトナム戦争で日本の新聞は国際的な活躍を見せ、その力を示した。毎日
の大森実外信部長らの連載『泥と災のインドネシア』や朝日の本多勝一記者の『戦場
の村』などで、アメリカの侵略によるベトナム戦争の実態が報道され、この戦争の不
条理さを世界に告発した。
北ベトナムのハノイに西側から一番乗りした毎日の大森実外信部長や朝日の秦正
流外報部長の記事に村して、ライシャワー駐日米大使は名指しで「ベトナム報道は公
正を欠いている」と一方的に非難して、大森部長は結局、退社に追い込まれた。
4
1972(昭和47)年4月には沖縄返還をめぐる外交交渉の秘密文書を外務省の女性
事務官から入手した毎日新聞政治部記者が逮捕されるという、いわゆる外務省機密
漏洩事件が起こり、アメリカのべトナム秘密文書事件での「ニューヨーク・タイムズ」
のケースと比較され、言論・表現の自由と国民の知る権利の問題が大きくクローズア
ップされた。
1973(昭和48)年、第一次オイルショックでそれまでの新聞産業の長期的な増勢、
拡大はストップし、「毎日」は77(昭和52)年に大幅な部数減から事実上倒産し、新会
社へ分離、再発足した。
また、東京新聞は67年に中日新聞へ譲渡され、69年には東京などの通勤サラリー
マンを対象にしたはじめての夕刊紙「夕刊フジ」が産経新開から、講談社も70年に
「日刊ゲンダイ」を創刊し、駅のスタンド売りの人気新聞となった。
アメリカでは「ワシントン・ポスト」 の若手記者たちが徹底した取材でニクソン大統領
を辞任に追い込んだウォ-ターゲート事件が有名だが、日本でこれに匹敵する調査
報道は1988(昭和63)年の「朝日」 のリクルート事件報道であった。
朝日新聞横浜支局がキャッチしたのは川崎市の助役がリクルート社から未公開株を
もらったという事件だが、警察は立件をあきらめていた。
「朝日」は独自に取材を進め、政府、官界、財界、マスコミ界にリクルート社が大量の
未公開株を配っていたことを突き止め、竹下首相の辞任までに発展、大物政治家ら2
0人以上が辞任や離党に追い込まれた。画期的な調査報道として高く評価されてい
る。
4 主役は新聞からテレビへ
ところで、明治以来、常にマスメディアの主役だった新聞はテレビの登場とともに立
場に微妙な変化が現れた。テレビは1953(昭和28)年に、日本で最初にNHK が本
放送を開始し、次いで民間放送の日本テレビが開局した。
テレビはまたたく間に普及して、5年後には100台を突破し、皇太子のご成婚(59年
4月)のパレード中継は人気を集め200万台に急増して、また民放30数局も開局し
ていた。
63年にはNHK の受信契約数は1500台で、普及率は75%を越えて、文字どおりテ
レビ時代を迎えた。
5
日本経済は1960年代から高度経済成長期に突入して、マスコミ産業全体の規模
拡大が70年代の半ばまで続いた。いわば「メディアの重層化現象」のなかで、それま
でマスメディアの中心に位置していた新聞は徐々に主役の座をテレビに奪われていく
ようになった。
1970年代には新聞の制作工程がコンピュータの技術革新によって一変した。編集
面にCTS(Computerized Typesetting System)が導入され、新聞制作から従来の鉛
活字や活版工程がなくなり、整理、校閲、組版の作業工程がコンピュータ化され、オン
ラインでの機械的な処理が可能となった。
75年には媒体別広告費ではテレビが新聞を抜いて、トップに立った。広告媒体とし
て新聞は2番手となってしまった。80年代に入るとテレビも報道番組を重視するよう
になり、テレビ朝日の「ニュースステーション」が登場しテレビ界ではニュース戦争が
はじまった。
90(平成2)年、「報道、ニュースは新聞よりもテレビで見る」と回答した視聴者の割
合が増え、報道面でもマスメディアの主役は新聞からテレビに移ってしまった。テレビ
の報道が新聞と肩を並べはじめ、ついには新聞のほうがテレビの後追いをするまで
になった。
1980年代以降、電子メディアの時代の幕開けによって、新聞はその圧倒的な取材
力と情報の質量を享に握っていることを生かして、文字を中心とした「新聞産業」から
「総合情報産業」への脱皮を目指して、多角的なメディア戦略を展開していった。
CATV、データベース、パソコン通信など、ニューメディアの展開に取り組み、メディア
の基幹産業としての地位を築いた。(終わり)
<以上は前坂俊之共著『(新版)メディア学の現在』世界思想社 2001 年4 月刊の「メ
ディアと検閲の転載です>
関連記事
-

-
『池田知隆の原発事故ウオッチ⑮』ー『最悪のシナリオから考えるー東京もチェルノブイリ第三区分入りか』
『池田知隆の原発事故ウオッチ⑮』 『最悪のシナリオから考えるー東京 …
-

-
日本リーダーパワー史(810)『明治裏面史』 ★『「日清、日露戦争に勝利」した明治人のリーダーパワー、リスク管理 、インテリジェンス㉕ 『日英同盟の核心は軍事協定で、そのポイントは諜報の交換』★『日露開戦半年前に英陸軍の提言ー「シベリヤ鉄道の未完に乗じてロシアの極東進出を阻止するために日本は一刻も早く先制攻撃を決意すべき。それが日本防衛の唯一の方法である。』
日本リーダーパワー史(810)『明治裏面史』 ★『「日清、日露戦争に勝利』した …
-

-
速報(43)『10分ですぐ分かる』◎日本民族の生死がかかる!『浜岡原発の虚実』『必見ビデオー広河隆一が語る』
速報(43)『10分ですぐ分かる』◎日本民族の生死がかかる!『浜岡原発の虚実』 …
-

-
速報「日本のメルトダウン」(487)「新しい日中関係を考える研究者の会」日本記者クラブ動画会見」「習主席、多国籍企業トップ称賛
速報「日本のメルトダウン」(487) &nb …
-

-
『F国際ビジネスマンのワールド・カメラ・ ウオッチ(231)』-『懐かしのエルサレムを訪問、旧市街のキリスト教徒垂涎の巡礼地、聖墳墓教会にお参りす』★『キリスト絶命のゴルゴダの丘跡地に設けられた教会内部と褥』
『F国際ビジネスマンのワールド・カメラ・ ウオッチ(231)』 ・ …
-
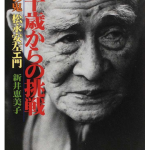
-
「Z世代のための日本リーダーパワー史研究』★『電力の鬼」松永安左エ門(95歳)の75歳からの長寿逆転突破力②』★『戦時下は「渇しても盗泉の水をのまず 独立自尊の心証を知らんや」と隠棲し茶道三昧に徹する』★『雌雄10年、75歳で「電気事業再編成審議会会長」に復帰』★『池田勇人と松永安左エ門の「一期一会」』★『地獄で仏のGHQのケネディ顧問』』
2021/10/06/日本史決定的瞬間講座⑪」記事再録 …
-

-
『F国際ビジネスマンの『世界漫遊・ヨーロッパ・カメラ・ウオッチ(17)』★『オーストリア・ウイーンぶらり散歩⑦』(2016/5)★『世界遺産/シェーンブルン宮殿』その広大な庭園に驚く(下)」』
2016/05/31 『F国際ビジネスマ …
-

-
世界、日本の最先端技術が『読める化』チャンネルー『国大慌て、「ノート7がここまで酷いとは!」-サムスンが落ちた「リコール10倍の陥穽」 』●『 シリコンバレーで起きている「食の異常事態」ー普通のレストランが消えつつある』●『人工知能の世界的権威が語る、テクノロジーがもたらす人類の未来』●『米グーグル、音声認識対応「Google Home」とWi-Fiルーター「Google WiFi」発表』●『「音声認識家電」は日本でもブレイクできるかー国内メーカーが揃い踏みしたが・・・』●『日本株、「暗黒の1987年」との共通点と相違点 ハンパない海外投資家の売り越しは終了?』
世界、日本の最先端技術が『読める化』チャンネル 韓国大慌て、「ノート7がこ …
-

-
『Z世代のための日本最高のリーダーシップ・西郷隆盛論⑤』★『米国初代大統領・ワシントンとイタリア建国の父・ガリバルディと並ぶ世界史の英雄・西郷隆盛の国難リーダーシップに学ぶ。★『奴隷解放』のマリア・ルス号事件を指導。「廃藩置県」(最大の行政改革)「士農工商・身分制の廃止」『廃刀令」などの主な大改革は西郷総理(実質上)の2年間に達成された』
2019/07/27 日本リーダーパワー史(858)/記事再録編集 …
-

-
速報(279)『日本のメルトダウン』☆仏独共同の国営放送局ARTE◎「フクシマ-最悪事故の陰に潜む真実」(ビデオ)
速報(279)『日本のメルトダウン』 仏独共同の国営放送局ARTE …
- PREV
- 正木ひろしの思想と行動('03.03)
- NEXT
- 「センテナリアン」の研究
