●「日本の新聞ジャーナリズム発展史(下)-『 昭和戦前期 ・軍ファシズムと新聞の屈伏』★『新聞と戦争「新聞の死んだ日」』★『 昭和戦後期・占領時代の検閲』★『「60 年安保からベトナム戦争まで」』★『「安保で死んだ新聞はトベトナム戦争でよみがえった」』
「日本の新聞ジャーナリズム発展史」(下)
2009/02/10
静岡県立大学国際関係学部教授
前坂 俊之
6 昭和戦前期 ・軍ファシズムと新聞の屈伏
昭和になり,1930 年代に入ると,経済恐慌や国内の政治混乱,社会不安,中国大陸での紛争などが重なって軍国主義ファシズムが台東し,右翼勢力と結託して新聞への圧力が高まってくる。
1931(昭和6)年9 月の満州事変の勃発以降,翌年の上海事変,5・15 事件によって海軍軍人らによって犬養毅首相が暗殺され,政党政治は終わりを迎えた。以後,15 年戦争に突入することになるが,新聞はこの間,警鐘を鳴らすどころか危機意識をあおり,軍部の暴走を容認し,積極的に支持する紙面展開を行った。
新聞による軍部批判や言論抵抗はほんの一部しかみられなかった。5・15 事件の時,「福岡日日新聞」(現在の西日本新聞)の編集局長・菊竹淳(六鼓)は「首相兇手に集る」「敢えて国民の覚悟を促す」などの社説で軍部もファッショを真正面からきびしく攻撃,「信濃毎日新聞」主筆の桐生悠々も社説「関東防空大演習を囁う」で軍部を批判したが,他の新聞の多くは軍部の顔色をうかがい,沈黙してしまった。
1936(昭和11)年の2・26 事件の際,首相官邸や国会を占拠した陸軍の反乱部隊は「東京朝日新聞」を襲撃した。そして,テロを恐れた新聞の抵抗はこれ以後みられなくなった。時代は戦時統制に入っていくが,新聞も軍,政府からきびしく統制された。
7 新聞と戦争「新聞の死んだ日」
政府は1940(昭和15)年,「1 県1 紙」の方針を打ち出し,新聞統合を強引に進めた。この方針により,それまで全国に1422 紙あった新聞は東京,大阪,北九州の全国紙以外は各県ではば1 県1 紙体制となり,55 紙までに減った。
現在の地方紙の勢力地図はこの時に出来上がったものであった。新聞社は国の宣伝機関と化し,言論の自由は完全に封殺され,真実の報道は一切できず,国や軍に命ぜられるままに書く,実質上の「国営新聞」となってしまった。
1941(昭和16)年5 月には新聞,通信,ラジオが加盟した「日本新聞連盟」が成立し,翌年には「日本新聞会」となり,国家総動員法によって新聞事業の権利の譲渡,廃止も許可制となり,編集,用紙,事業のすべてを政府に握られ,記者の登録制が実施された。
太平洋戦争中の言論統制は30 以上の法規によって,新聞はがんじがらめにされ,ウソの代名詞となった「大本営発表」以外は一切書けない状態となってしまった。また物資の欠乏,用紙不足によって新聞のページ数は減り,1944(昭和19)年3 月からは夕刊も廃止され,新聞は死んだ状態となってしまった。
8 昭和戦後期・占領時代の検閲
1945(昭和20)年8 月15 日,日本は敗北し,戦争は終結した。敗戦後,連合国軍総司令部(GHQ)は旧日本帝国政府,軍による言論取り締まりの法規を全廃,言論の自由は回復された。しかし,GHQ は「公安を害するおそれのある事項を印刷することを得ず」など10 か条からなるプレス・コードを発表し,占領政策の批判や軍国主義的な発言に対してはきびしい検閲,統制を実施することになった。
戦後の新聞は戦前,戦中の報道に対する反省からスタートした。
GHQ の民主化の後押しもあり,新聞各社では一斉に戦争責任の追及の動きが起こり,社内民主化運動が吹き荒れた。1946(昭和21)年7 月ごろまでに,ほとんどの新聞社で従業員組合が結成された。
「朝日」は社長以下の幹部の辞任と相まって,「国民と共に立たん」という宣言を掲げ,再出発した。6 年半の占領期間中,GHQ によって事前検閲や事後検閲が行われた。検閲は戦前の日本のように伏せ字や削字によって明らかに検閲されたことが読者に分かるものではなくて,言い換えや文章をまったく書き換えて分からないようにした,きわめて巧妙なものであった。
1950(昭和25)年6 月の朝鮮戦争の勃発で,米ソの冷戦は頂点に達して反共主義が高まった。GHQ は「アカハタ」など日本共産党の新聞,雑誌などを発行停止にし,新聞,放送各社の従業員約700 人を突然解雇するという,いわゆるレッドパージが行われた。
1951(昭和26)年9 月,サンフランシスコ講和会議によって,翌年4 月,占領体制にやっと終止符が打たれた。用紙統制が撤廃された。
1951(昭和26)年からは本格的な自由競争の時代に入った。全国紙と地方紙の競争が一段と激化したため,「朝日」「毎日」「読売」はそれまで国内外ニュースの配信契約を結んでいた共同通信社から一斉に脱退してしまった。
9・「60 年安保からベトナム戦争まで」
1960(昭和35)年,戦後最大の国民的運動といわれた60 年安保闘争が起こった。6 月15 日,国会周辺を取り囲んだ学生デモ隊が国会構内に乱入し,機動隊と激しく衝突して,流血の惨事を引き起こし女子学生1 人が死亡,300 人以上が負傷した。
この2 日後に在京の新聞社7 社(「朝日」「毎日」「読売」「日本経済」「産経」「東京」「東京タイムズ」)は朝刊1 面に「暴力を排し議会主義を守れ」と題する共同宣言を掲げた。
「流血事件は,その事の依ってきたる所以を別として,議会主義を危機に陥れる痛恨事であった。……いかなる政治的難局に立とうと,暴力を用いて事を運ばんとすることは断じて許されるべきではない」と全学連の行動をきびしく批判した。
この7 社共同宣言はその後,地方紙48 紙にも転載された。空前の勢いで盛り上がっていた大衆運動で,国民の間に安保改定を強行採決した岸内閣への退陣要求が圧倒的に大きくなり,新聞もこれを支持していただけに,突然手のひらを返した主張であった。
「その事の依ってきたる所以を別にして」「これまでの争点をしばらく投げ捨て」とデモ隊の暴力だけを非難,その姿勢を逆転してしまった。
戦争中にいったん死んだ新聞は,この共同宣言によって「再び死んだ」ともいわれた。
10・「安保で死んだ新聞はトベトナム戦争でよみがえった」
1965(昭和40)年から始まったベトナム戦争では、日本の新聞は国際的な活躍を見せ,その力を示した。「毎日」連載「泥と炎のインドシナ」や「朝日」の本多勝一記者の「戦場の村」などのルポルタージュで,アメリカの侵略によるベトナム戦争の実態が生々しく報道され,この戦争の不条理さを世界に告発した。北ベトナムのハノイに西側から一番乗りした「毎日」の大森実外信部長や「朝日」の秦正流外報部長の記事に対して,ライシャワー駐日米大使は名指しで「ベトナム報道は公正を欠いている」と一方的に非難して,大森部長は結局,退社に追い込まれた。
1972(昭和47)年4 月,沖縄返還をめぐる外交交渉の秘密文書を外務省の女性事務官から入手した毎日新聞政治部記者が逮捕されるという,いわゆる外務省機密漏洩事件が起こり,アメリカのベトナム秘密文書事件での「ニューヨーク・タイムズ」のケースと比較され,言論・表現の自由と国民の知る権利の問題が大きくクローズアップされた。
1973(昭和48)年,第一次オイルショックでそれまで一貫して続いていた新聞産業の長期的な増勢・拡大はストップし,「毎日」は1977(昭和52)年に大幅な部数減により事実上倒産し,「新社」として再発足した。
それに先立ち,「東京新聞」は1967(昭和42)年に「中日新聞」へ譲渡された。1969(昭和44)年には産経新聞が首都圏の通勤サラリーマンを対象にした「夕刊フジ」を発行,講談社も1970(昭和45)年に「日刊ゲンダイ」を創刊し,タブロイド紙が駅のスタンド売りの人気新聞となった。
アメリカでは「ワシントン・ポスト」の若手記者たちが徹底した取材でニクソン大統領を辞任に追い込んだウォーターゲート事件が有名だが,日本でこれに匹敵する調査報道は,1988(昭和63)年の「朝日」のリクルート事件報道であった。
朝日新聞横浜支局がキャッチしたのは川崎市の助役がリクルート社から未公開株をもらったという事件だったが,警察は立件をあきらめていた。
しかし「朝日」は独自に取材を進め,政府,官界,財界,マスコミ界にリクルート社が大量の未公開株を配っていたことを突きとめ,竹下首相の辞任までに発展し,大物政治家ら20 人以上が辞任や離党に追い込まれた。こうした一連の取材・報道は画期的な調査報道として今日も高く評価されている。
奪われた主役の座 ところで,明治以来,常にマスメディアの主役だった新聞は,テレビの登場とともにその立場に微妙な変化が現れた。
テレビは1953(昭和28)年に日本で最初にNHK が本放送を開始し,次いで民間放送の日本テレビが開局した。テレビはまたたく問に普及して,5 年後には100 万台を突破し,皇太子のご成婚(1959・昭和34 年4 月)のパレード中継をきっかけに200 万台に急増,民放30 数局が開局した。1963(昭和38)年にはNHK の受信契約数は1,500万台で,普及率は75%を越えて,文字通りテレビ時代を迎えた。
11・コンピュータ化された新聞
日本経済は1960 年代から高度経済成長期に突入して,マスコミ産業全体の規模拡大が1970 年代の半ばまで続いた。いわば「メディアの重層化現象」の中で,それまでマスメディアの中心に位置していた新聞は1970 年代から,徐々に主役の座をテレビに奪われていくようになった。
1970 年代には新聞の制作工程がコンピュータの技術革新によって一変した。編集面ではCTS(Computerized Typesetting System)が導入され,新聞制作から従来の鉛活字や活版工程がなくなり,整理,校閲,組版の作業工程がコンピュータ化され,オンラインでの機械的な処理が可能となった。
1975(昭和50)年には媒体別広告費ではテレビが新聞を抜いて,トップに立った。広告媒体としては新聞は二番手となってしまった。
1980 年代に入るとテレビも報道番組を重視するようになり,テレビ朝日の「ニュースステーション」が登場し,テレビ界ではニュース戦争が始まった。その結果,1990(平成2)年になると「報道,ニュースは新聞よりもテレビで見る」という視聴者の割合が増え,報道面でもマスメディアの主役は新聞からテレビに移ってしまった。
テレビの報道が新聞と肩を並べはじめ,ついには新聞の方がテレビの後追いをするまでになった。
1980 年代以降,電子メディア時代の幕開けによって,新聞はその圧倒的な取材力と情報の質量を一手に握っていることを生かして,文字を中心とした「新聞産業」から「総合情報産業」への脱皮を目指して,多角的なメディア戦略を展開していった。CATV,データベース,インターネットなど,ニューメディアに積極的に取り組み,メディアの基幹産業としての地位を保持していった。
<参考文献>
山本文雄編(1981)『日本マス・コミュニケーション史[増補]』東海大学出版会
春原昭彦(1980)『三訂一日本新聞通史』新泉社
内川芳美・新井直之編(1983)『日本のジャーナリズム』有斐閣
高木教典・新井直之編(1974)『講座 現代ジャーナリズムⅠ歴史』時事通信社
前坂俊之(1989)『兵は凶器なり一戦争と新聞1926-1935』社会思想社
前坂俊之(1991)『言論死して国ついに亡ぶ一戦争と新聞1936-1945』社会思想社
原寿雄(1997)『ジャーナリズムの思想』岩波書店
渡辺武達他編(1997)『メディア学の現在(改訂版)』世界思想社
<以上は天野勝文・前坂俊之ら共著「現代マスコミ論のポイント」学文社1999年5月刊に掲載されたものです>
関連記事
-

-
知的巨人の百歳学(103)-長崎原爆に被災地に「平和祈念塔」を創った彫刻家・北村西望(102歳)の『たゆまざる 歩み恐ろし カタツムリ』★『日々継続、毎日毎日積み重ねていくと、カタツムリのように1年、2年、10年、50年で巨大なものができる』
「わたしは天才ではないから、人より五倍も十倍もかかるのです」 「いい仕事をするに …
-

-
速報(114)『日本のメルトダウン』まとめ<世界はムチャクチャじゃ>『原発放射能』『先進国の借金財政』『中国情報隠ぺい』
速報(114)『日本のメルトダウン』 ★NAVERまとめ9本!<世界はムチャクチ …
-

-
「日本風狂人伝⑥歌人・若山牧水「生来、旅と酒と寂を愛し、自ら三癖と称せしが命迫るや、静かに酒を呑み・」
日本風狂人伝⑥ 2009,6,22 歌人・若山牧水 「生 …
-
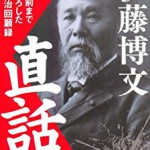
-
日本リーダーパワー史(845)★記事再録『伊藤博文の『観光立国論』ー『美しい日本の風景・文化遺産こそ宝』<百年前に唱えた伊藤首相のビジネス感覚を見習え>
日本リーダーパワー史(845) 2010/12/08の記事再録日本リー …
-

-
『Z世代のための日本興亡史研究④』★『日本海海戦完勝の<東郷平八郎神話>が40年後の<太平洋戦争開戦と敗北>の原因の1つになった』★『ネルソン神話と40年後の東郷神話の同一性』
第2次近衛内閣(1940年7月22日から1941年7月18)の和戦 …
-

-
『リーダーシップの日本近現代史』(59)記事再録/『高橋是清の国難突破力①』★『日露戦争の外債募集に奇跡的に成功したインテリジェンス
2011/07/10 / 日本 …
-

-
日本メルトダウン脱出法(612)「モバイル革命100年で3度目の大変革「E2E経済」の衝撃」『ギリシャ総選挙とユーロ危機の再来(英FT紙)
日本メルトダウン脱出法(612) 2014年よ、さ …
-

-
『明治裏面史』 ★ 『日清、日露戦争に勝利した明治人のリーダーパワー,リスク管理 ,インテリジェンス㊹★『明石謀略戦((Akashi Intelligence )の概略と背景』★『ロシアは面積世界一の大国なので、遠く離れた戦場の満洲、シベリアなど極東のロシア領の一部を占領されても、痛くも痺くもない。ロシアの心臓部のヨーロッパロシアを突いて国内を撹乱、内乱、暴動、革命を誘発する両面作戦を展開せよ。これが明石工作』
『明治裏面史』 ★ 『日清、日露戦争に勝利した明治人のリーダーパワー, リスク …
-

-
片野勧の衝撃レポート(52)被爆記憶のない世代は、被爆体験をどう伝えるか(上)
片野勧の衝撃レポート(52)太平洋戦争とフクシマ(27) 『なぜ悲劇は繰り返 …
-

-
速報(131)『田中三彦氏、中手聖一氏と小出裕章氏が講義 (第2回 核・原子力のない未来をめざす市民集会)』
速報(131)『日本のメルトダウン』 『田中三彦氏、 …
