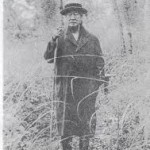大阪地検特捜部の証拠改ざん事件を読み解く④死刑・冤罪・誤判事件ー30年変わらぬ刑事裁判の体質②
大阪地検特捜部の証拠改ざん事件を読み解くために④
裁判官・検事・弁護士・新聞記者の徹底座談会
死刑・冤罪・誤判事件ー30年変わらぬ刑事裁判の体質②
月刊『サーチ』1983年9月の再掲載
<出席者=樋口 和博(弁護士)安倍 治夫(弁護士)佐伯 仁(弁護士)前坂 俊之(『毎日新聞』記者>
証拠を見せずにたとえ嘘でも聞いてみる尋問のコツ
安倍 樋口先生、尋問の技術とか、そういう訓練は、いまどうなっているんですか。私は帝銀事件の高木一先生についたんですが、あの人が次席の時に私が札幌に赴任したんです。そこで、いろいろ教えられましたね。
たとえば、放火した人が靴下をはいているんです。靴下を押収すると、そこに泥がついている。ふつうの刑事だと、「おい、これはおまえの靴下だろう、泥の上に乗ったからこびりついてる」と、眼の前に証拠の靴下をつきつけるんですね。
よくテレビドラマでやるでしょう。ところが、高木先生は証拠は絶対つきつけちゃいかん、と言うんです。靴下は絶対に見せない。見せないでいて、「あんた何はいていた」ってまず聞くんですね。そうすると「靴下です」という。それでもまだ、「これだろう」なんて言わない。「どんな色のだ」「ええ、青いやつでシマがあったと思うんです」とくる。「他になんか覚えていない? 靴下のことで」。そこで「ちょっと爪のばしてたものだから、小指のところに穴があいてたみたいです」なんて言いだす。
それでも「ほら、これだろう」とは言わない。机の下で手にもった靴下をひっくり返したりして見ているんですね。それから「油みたいなものを踏んだか」ってね。「ええ、何かヒヤッとしました」「ヒヤッとしたってどのへんだ。足先か?」
「いえちょうど土踏まずのへんです」。それでまた靴下を見ると、土踏まずのところにベタッと油がついてるでしょう。とうとう最後まで見せないで、法廷にも出さない、そのままでとっとくというの。これが正しい尋問の方法だというんだね。
まず相手に具体的なことをたくさん言わせる。わざとしゃべらせるんですね。こういうふうな検察官だと、相手もそう嘘はないわけですよね。それを近ごろの人は証拠をつきつけてね、自白するとワッと喜ぶでしょう。これが間違い。だから私どもは自信ありますよ。
とにかくしつこく無駄なこと聞くんです。そうすると最近の裁判官は、先生、もうそのくらいでいいですよって、こういう、バカな人がいるわけ。そうじゃないんだよね。嘘をついている場合には、うんと嘘を言わせてみるんです。だんだん状況に合わなくなってくるでしょう。本当のことでもとにかく細かく聞いて、相手にも正確に思い出させるようにするんです。それを近ごろの検察官や裁判官だといやがるんです。-
樋口 たしかに大事なことですな。いわゆる状況をまずかためるってことだね。
安倍 やっぱり無駄なことを言わしてみないと、本当か嘘かわかりませんよ。
樋口 たしかに弁護士になってみて、そういうことを感じるよ。裁判官っていうのは出て来たお膳を食べるだけでしょう。ところが弁護士になってみますと、自分でごちそうを作るわけです。作ってそうして裁判所に見せて、判断を求めるわけですね。その達いってのはつくづく感ずるね。判事ってのは、作ることは知らないで、食べることだけ知ってるんだってこと。
すんなり無罪にしたらおのれの首が危い
前坂 樋口先生、免田事件の場合、昭和三十一年八月にいったん再審開始が決定しながらそのあと決定が取り消されているんですが、やはけ再審を開始することについての、裁判官の抵抗といいますか、先輩の誤りを自分が改めるということに対して、まだ抵抗があるように思えるんですが。
樋口 いや、ないはずですよ。だからたとえば名古屋の吉田事件のときに、裁判長がお詑びをしたでしょう。
安倍 あのときはずい分上層部から非難されたみたいだね。
樋口 あれは余分なことですよ。私はそう思う。詑びることなんかないです。それからね、この頃よく無罪の判決のあとにくっつけて、「まだ疑わしい部分が残っているが」、なんてことを言いますね。あれだって、言うべきことではないです。裁判官というものは、判決以外のことを言うもんじゃないですよ。
本誌 〝疑わしきは罰せず〃という法の大鉄則に照らせば、無罪を言い渡しておいて、なお疑いが残るという言い方はおかしいと思いますね。
安倍 負け惜しみみたいで、みっともないね。俺はまだ官憲側だぞ、ということをほのめかして、自分の地位を保全しょうってわけでしょう。すんなり無罪にしたら己れの首が危いと思ってるんだね。そういう気持があるからあんなことを言う。
佐伯 上ばっかり見ている裁判官の典型ですよ。社会のいろんな出来事に対する理解がないですよ。
樋口 それと、旧刑訴法のころには一度、有罪判決が出たものに無罪を言い渡すことに、裁判官が非常に抵抗があったようです。なぜかっていうと、裁判官は法務大臣の監督下にあったんです。
検事も同様。だから無罪でも言い渡してごらんなさいよ。あの裁判官はだめだ、役に立たないからどっか田舎へすっとばせっていうのが普通のことでした。法務省が人事権を持っていますからね。
裁判官と言えども、自分の身がかわいくて無罪を言い渡そうにも言い渡せなかった風潮がありましたね。よほど気骨のある人ならばやりますけどね。そういうのが、旧刑訴法のやり方ですよね。けれども戦後の今日、新刑訴法なってからは、無罪を言い渡すことについては、まず裁判官も全く抵抗がなくなったと思うな。私の場合も何の抵抗もありませんでしたね。それでまた、無罪を言い渡したからといって、裁判官がとくに不利益をうけることは絶対ありません。
安倍 先輩のしたことを批判しちゃならんという遠慮みたいあるかっていうことについて
は、私はないと思うんです。その点、裁判官は非常にドライにものを考える。
そんなことで遠慮するような細かいセンスを持っていないと思います。むしろ冷たい批判的な感覚.の方が強いと思います。
佐伯 官僚が怠け者になっちゃってるのではないか。普通の人間かち自分を隔絶したところにおいておくから、人間の日常行動の感じ方、事実に対する認識力、こういうのがずーっと欠落していく官僚の機構の中だけにいるから、わが身の安泰ぽっかり心配して、怠け者になるんです。自分たちの世界だけでしか通用しない考え方で、すべての物事をはかろうとする。自分以外の世界に眼をむけようとはしない。
安倍 理論的に可能なものは可能だと思うんですよ。ところが、免田事件にしてもね、事
件直後に免田君が寒中、零下何度という川に入って、血のついた衣類を洗って、たき火をして干したということになっていますね。現場の状況を見た人なら誰だってわかることですが、あんな場所で火なんかたいたら、まず消防が気づくし、人は集まってくるし、田舎ですから。第一、真冬の川なんかに素っ裸になって入ったら、すぐ風邪ひいちゃう……(笑)。
たき火で乾かした衣類は繊維の間に炭素がいっぱいつまっている転んです。それに煙でいぶすわけだから匂いがしみこんでいるものですよ。血液なんか、普通のドロみたいに、水で洗ったぐらいじゃ落ちません。必ず残るんだ。そういうところを裁判官が気がつけば、おかしいと思うはずですよ。ところが気がつかない(笑)。
佐伯 検事も気がつかなかったというんです。いかにあのころの検事はなまけてたかっていうことになりません
か。
安倍 そういうところのね、深く現実をみるっていう親切ってものがないですね。人間一人の命がかかっているんだから。人間っていうのはふつうそういう時にどういう行動をするか、常識的なものがあるんですよ。アリバイ捜査にしても、もっと常識的な線をもってしっかりやらないといかん。
そういうことを何もしないで、検察側の言い分を鵜呑みにして、現実的、常識的に不可能な論理をまことしやかに積み上げていくから冤罪が起こるんです。
裁判官に暇がないとまず安易に強い方を勝たせる。それで文句があったら控訴するだろうと
佐伯 ちかごろやっぱり司法官の質が落ちてきた……(笑)。いや、樋口先生のころはまだ戦前ですから。真実探求の意欲のある人々がたくさんおられましたから、信用できるんです。今どきの人は、自分の出世ばかり考えているようにみえるし、そうでなくても、同僚意識っていうかね、検事のいうことに、嘘はないだろうって安易に受けと
めている。私にしてみればとんでもない話ですよ。
前坂 しかしですね。例えば免田事件、財田川事件、松山事件とみていきますと、誤判の構造が驚くほど似ている。ぼくら素人でも、調書や記録を丹念に読めば、どの事件もそれほどの難事件とは思えないんですが。
佐伯 難事件じゃないですよ。簡単ですよ。私も免田事件を十何年やってきたけど、結局、官僚の非常識ですよ、結論は。裁判官の非常識、捜査官の無知、それが重なってるわけです。権力が一回、非常識で判断を示すと、この非常識は権力構造の中に定着するものだから簡単には破れない。それを破るために苦労したんです。ぽくらが苦労したのは常識と非常識の戦いだったんです。原理はものすごく簡単です。
樋口 いや、ぼくはね、ちょっとそれについて、私は司法と、つまり裁判所と他の官庁との違いはあると思いますよ。検事は検事で彼らの中に原則がありましてね、それは上命下従いろいろあると思う。ところが、裁判官だけはそういう上がどうの下がどうのとい
う、これはないですよ。これだけはぼくは信じてほしい。
裁判官ぐらい孤独なものはないんです。誰に救いを求めることもできない。他の行政官庁なんてものはね、課長が判を押して、部長が判を押して、局長が押すという具合に順番に判を押すでしょ。みんな責任ある人が押したんだから、下の方は上の方でもちゃんと承知してるんだからって安心してるでしょう。裁判官に関するかぎりは、これはできない。これだけは世の中の人に、判ってもらいたいと思うんだ。
佐伯 ところが戦後の先輩たちはね、そうでもないですよ。気楽なもんですよ。検事のいうことにのっかって安全な方で判断するだけで物事を真剣に見極めようという努力をしてないのではないか。鑑定ひとつとりあげても真剣に見極めようとしない態度がみえる。
安倍 鑑定はもう一ペん見極めなきゃ、我々が聞いていても本当に医学部を出たのかって疑りたくなるようなものがありますからね。質問には答えない、関係のないことばかり言って、これぐらいのことを医者はやんなきゃ明日から商売になりませんよっていう必要論っていうかねてそんなもんで決められたらたまったもんじゃないですよ。
佐伯 安倍先生に紹介していただいた名古屋大の矢田昭一先生ね、免田事件の。僕らは科学の知識はないけど、矢田先生の説明は非常にわかりやすいでしょう。その論理をふまえて、それまでに出された鑑定を見ると、いったいこの判断はどこが科学なんだろうっていうぐらいで、仮説と理屈の展開だけなんですよね。科学性がぜんぜん見あたらない。こんなものにのっかったらえらいことになるなってことに気がついたことがあります。
安倍 悪いことに民事の場合、裁判官が変わるでしょう。膨大な事件で一緒に検証に立ち会った裁判官はまだいいですよ。二人目、三人目と替わって最後があんまり暇がないっていうようなときには、まず安易に強い方を勝たせる。医者とか、国家権力とか、大会社、それで文句があったら、相手方はもう一回控訴するだろうぐらいに考えて、強いものに味方した裁判になっちゃぅ。裁判官になった以上は、ひとつ大会社をこらしめてやるぐらいのそういう気持がほしいですね(笑)。
樋口 当然よ、それやあ。それが裁判官の気魄ですよ。
安倍 今はそういう気魄の人、いないですね。
樋口 いやあ、いないことはないよ。
(つづく)